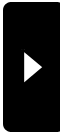2015年02月05日
京都市国民健康保険料引き下げへ~団長談話発表
党市会議員団は本日、国民健康保険料の引き下げについて、以下、団長談話を発表しました。
昨日開かれた平成26年度第3回京都市国民健康保険運営協議会において、京都市は国民健康保険料の引き下げと最高限度額の引き上げ方針を発表しました。2月市会へ提案される方向とされています。
その内容は医療分、後期高齢者支援分、介護分にかかる保険料率を全て引き下げるもので、全てで保険料率を引き下げるのは制度発足以来、初めてのことです。これにより、被保険者一人あたり年間平均で2532円の保険料引き下げとなります。また、保険料軽減措置の対象世帯の所得基準額改定により、保険料5割軽減、2割軽減の対象者の拡大も打ち出されています。
高すぎる国民健康保険料の引き下げは積年の市民の願いであり、党議員団も市民とともに繰り返しその実現を求めてきました。最高限度額の引き上げはあるものの、9割超の被保険者の負担軽減は、その願いに応えるものであり、国保料の引き下げを求める運動の成果です。
しかしながら、今回の提案は、歳入超過分14億円について保険料負担軽減は7億円にとどめ、残り2分の1は一般会計繰入金の縮小に充てるものとなっています。これは、国保の都道府県単位化を前提とした自治体独自繰り入れの後退を図る国の方針に沿うものであり、認められません。市民の国保料引き下げの切実な願いに正面から応えるべきです。
党議員団は引き続き、更なる国保料の引き下げ実現と国民健康保険の都道府県単位化の中止にとりくむものです。
「医療費の心配をなくし、いのちを守る署名」
―①国保料の1万円以上の引き下げ。国民健康保険制度の京都府への一元化は中止すること。
②子どもの医療費を入院も通院も中学校卒業まで無料にすること。
③老人医療費助成制度(マル老)を存続させ、対象年齢を74歳まで拡充すること。
にとりくんできましたが、さらに広げて、「いのち守る」願い実現へがんばります!
昨日開かれた平成26年度第3回京都市国民健康保険運営協議会において、京都市は国民健康保険料の引き下げと最高限度額の引き上げ方針を発表しました。2月市会へ提案される方向とされています。
その内容は医療分、後期高齢者支援分、介護分にかかる保険料率を全て引き下げるもので、全てで保険料率を引き下げるのは制度発足以来、初めてのことです。これにより、被保険者一人あたり年間平均で2532円の保険料引き下げとなります。また、保険料軽減措置の対象世帯の所得基準額改定により、保険料5割軽減、2割軽減の対象者の拡大も打ち出されています。
高すぎる国民健康保険料の引き下げは積年の市民の願いであり、党議員団も市民とともに繰り返しその実現を求めてきました。最高限度額の引き上げはあるものの、9割超の被保険者の負担軽減は、その願いに応えるものであり、国保料の引き下げを求める運動の成果です。
しかしながら、今回の提案は、歳入超過分14億円について保険料負担軽減は7億円にとどめ、残り2分の1は一般会計繰入金の縮小に充てるものとなっています。これは、国保の都道府県単位化を前提とした自治体独自繰り入れの後退を図る国の方針に沿うものであり、認められません。市民の国保料引き下げの切実な願いに正面から応えるべきです。
党議員団は引き続き、更なる国保料の引き下げ実現と国民健康保険の都道府県単位化の中止にとりくむものです。
「医療費の心配をなくし、いのちを守る署名」
―①国保料の1万円以上の引き下げ。国民健康保険制度の京都府への一元化は中止すること。
②子どもの医療費を入院も通院も中学校卒業まで無料にすること。
③老人医療費助成制度(マル老)を存続させ、対象年齢を74歳まで拡充すること。
にとりくんできましたが、さらに広げて、「いのち守る」願い実現へがんばります!
category:市議会
2014年11月28日
代表質問にたちました
今日は京都市会11月市会で日本共産党会派から代表質問にたちました。
取り上げた内容は以下の点です。
・原発再稼働について避難計画は全市域を対象とした計画を
・市営保育所の民間移管について
・学校給食の地産地消推進や食器、中学校給食について
・北泉通への架橋中止や左京区役所移転と足の確保について
○原発再稼働をめぐっては藤田副市長が答弁しました。
これまでから「中期的には脱原発依存、短期的には稼働性の必要性を明らかにし、万全の安全性を確保したうえで、地域住民の理解を得ることが必要である」と述べてきた京都市。
今回はそれに加えて、「立地自治体だけでなく原発から30Km 圏内のUPZを含む関係自治体への十分な説明と理解が必要」と述べ、「市独自に、また関西広域連合として国に申し入れている」と答弁しました。
つまり、30Km 圏内のUPZを含む関係自治体=京都市の理解が必要という認識を議会で表明したことになります。
どのように市独自に国に申し入れているのか、重ねての追及が必要です。
そして、周辺自治体として理解を求められたとき、京都市が原発再稼働にどのように考えるのかが焦点になり、市長は原発ゼロ、再稼働反対の立場に立つのかどうか、その立場が鋭く問われることになります。
○公営保育所の民間移管ついては、子育て支援拠点事業について、箇所数の減少で支援が薄まるとの私の指摘に「広域的ネットワークづくりや子育て家庭への訪問実施で機能強化を図る」と答弁がありました。具体的な内容も含めて、更に追及していきたいと思います。
検証がないと追及してきましたが、「今後とも保護者、移管先法人、市の三者協議会での意見や検証をふまえて円滑な移管にとりくむ」と円滑な移管への検証に検証を矮小化する答弁を行いました。これについても、さらに追及したいと思います。
○給食をめぐっては食器について「より味わいを感じることができる食器へ更新を検討する」と教育長が答弁しました。
長年の市民の願いが実を結びつつあります。KBS放送では、ペン食器などへの順次更新に10億円程度、3か年での更新が検討されていると報じられました。
中学校給食については自校調理の全員給食は全く考えていないと述べましたが、アルマイト食器についても同じような状況から改善に向けて大きく踏み出したように、粘り強く声を上げ、運動を広げ、論戦していくことが大事だと感じました。
○左京区役所への公共交通の確保については、自治体要求連絡会のアンケートで7割もが「移動に困る場所」を区役所としていることを指摘。
これまでから、南部地域への支所設置など改善を求めてきたのに、旧左京区役所跡地売却、同駐車場跡地売却、岩倉出張所廃止と解決が図られていないと追及しました。
「北泉橋を架橋すれば左京区役所へのアクセス向上に寄与する」と交通局長が答弁しましたが、肝心のシャトルバスなどの公共交通・市バスの改善については「運航に見合う利用が見込めず難しい」とゼロ回答。移転後の路線変更を説明しました。その路線変更をふまえた上で「区役所が不便だ」と区民が考えているのに、バスを走らせず、なにおか言わんや。あまりにお粗末です。区役所は行政サービスの最前線、そこへの公共交通確保は市民が行政サービスを受ける権利保障にかかわる問題であるという認識が欠落している。重大です。
取り上げた内容は以下の点です。
・原発再稼働について避難計画は全市域を対象とした計画を
・市営保育所の民間移管について
・学校給食の地産地消推進や食器、中学校給食について
・北泉通への架橋中止や左京区役所移転と足の確保について
○原発再稼働をめぐっては藤田副市長が答弁しました。
これまでから「中期的には脱原発依存、短期的には稼働性の必要性を明らかにし、万全の安全性を確保したうえで、地域住民の理解を得ることが必要である」と述べてきた京都市。
今回はそれに加えて、「立地自治体だけでなく原発から30Km 圏内のUPZを含む関係自治体への十分な説明と理解が必要」と述べ、「市独自に、また関西広域連合として国に申し入れている」と答弁しました。
つまり、30Km 圏内のUPZを含む関係自治体=京都市の理解が必要という認識を議会で表明したことになります。
どのように市独自に国に申し入れているのか、重ねての追及が必要です。
そして、周辺自治体として理解を求められたとき、京都市が原発再稼働にどのように考えるのかが焦点になり、市長は原発ゼロ、再稼働反対の立場に立つのかどうか、その立場が鋭く問われることになります。
○公営保育所の民間移管ついては、子育て支援拠点事業について、箇所数の減少で支援が薄まるとの私の指摘に「広域的ネットワークづくりや子育て家庭への訪問実施で機能強化を図る」と答弁がありました。具体的な内容も含めて、更に追及していきたいと思います。
検証がないと追及してきましたが、「今後とも保護者、移管先法人、市の三者協議会での意見や検証をふまえて円滑な移管にとりくむ」と円滑な移管への検証に検証を矮小化する答弁を行いました。これについても、さらに追及したいと思います。
○給食をめぐっては食器について「より味わいを感じることができる食器へ更新を検討する」と教育長が答弁しました。
長年の市民の願いが実を結びつつあります。KBS放送では、ペン食器などへの順次更新に10億円程度、3か年での更新が検討されていると報じられました。
中学校給食については自校調理の全員給食は全く考えていないと述べましたが、アルマイト食器についても同じような状況から改善に向けて大きく踏み出したように、粘り強く声を上げ、運動を広げ、論戦していくことが大事だと感じました。
○左京区役所への公共交通の確保については、自治体要求連絡会のアンケートで7割もが「移動に困る場所」を区役所としていることを指摘。
これまでから、南部地域への支所設置など改善を求めてきたのに、旧左京区役所跡地売却、同駐車場跡地売却、岩倉出張所廃止と解決が図られていないと追及しました。
「北泉橋を架橋すれば左京区役所へのアクセス向上に寄与する」と交通局長が答弁しましたが、肝心のシャトルバスなどの公共交通・市バスの改善については「運航に見合う利用が見込めず難しい」とゼロ回答。移転後の路線変更を説明しました。その路線変更をふまえた上で「区役所が不便だ」と区民が考えているのに、バスを走らせず、なにおか言わんや。あまりにお粗末です。区役所は行政サービスの最前線、そこへの公共交通確保は市民が行政サービスを受ける権利保障にかかわる問題であるという認識が欠落している。重大です。
category:市議会
2014年11月06日
公営保育所の民間移管について教育福祉委員会でとりあげました。
昨日の教育福祉委員会で京都市から新たに6カ所の公営保育所の民間移管をすすめる「基本方針」について報告がありました。
市民意見を受けて、「基本方針案」の「案」をとった「方針」を報告したものです。
○ 「基本方針案」によせられた市民意見は2043 人・2679件という規模になりました。
しかも、「民間移管に関することの意見」1851件のうち肯定的意見は20件。反対・否定的・慎重意見が1831件=99%が反対・否定的・慎重意見ということになります。
すでに、陳情が出された「基本方針案」の見直しを求める署名は短期間に1万4000筆をこえました。
私は委員会の質問で「この『市民意見』がどう反映された『方針』になったのか」質しました。
当局は「反対意見が多いと感じている」としたものの、民間移管方針を変えることは「ありえない」と答えました。
以前の委員会で「基本方針案全体が市民意見募集の対象」ということは確認しています。
「ありえない」ことが「ありえない」。
何のために市民から意見を聞いているのか、怒り心頭です。
○一方で、みなさんの運動で、方針案から「何も変えることなし」という市民世論ではないと当局を思わせた反映がありました。
3つの点での変更です。
①障害をもつお子さんに対応した職員加配の公・民統一化
②地域子育て支援拠点としての機能強化
③重度の障害があるなど特に配慮を要する子どもが在籍する場合のより丁寧な引継ぎ
何れも、具体的内容については鮮明ではありませんでしたが、地域子育て支援拠点については「地域子育て支援拠点事業を担ってきた公営を6カ所移管してどのように『機能強化』するのか」との質問に、「地域子育て支援事業の後退はあり得ない」と述べました。引継ぎについては「より丁寧な」とは何を指すのかという点については「重度の障害がある児童の担当は継続できるようにする」との主旨の答弁でした。
○「6カ所の民間移管方針そのものを変えることはありえない」という当局の答弁をどう見るのか。これは、つまり、市政運営上の根本姿勢ということなのでしょう。
今でも1割しかない公営保育所を更に減らし、そこが担ってきた役割、機能を後退させ、必要な福祉を削減する。民間保育所も苦慮している保育士確保という点での京都市の貢献も大幅に後退させる。これは、市政のかじ取りとして間違っています。
京都市行政の在り方「民間にできることは民間に」と言い「民間にできないことまで民間に」民間移管ありきでひた走る。それが、市民福祉に後退をもたらすことは明らかです。
来年のいっせい地方選挙と再来年の市長選挙を見すえて、市政の在り方を根本から問う運動を広げることが変化を生むと確信しています。
市民意見を受けて、「基本方針案」の「案」をとった「方針」を報告したものです。
○ 「基本方針案」によせられた市民意見は2043 人・2679件という規模になりました。
しかも、「民間移管に関することの意見」1851件のうち肯定的意見は20件。反対・否定的・慎重意見が1831件=99%が反対・否定的・慎重意見ということになります。
すでに、陳情が出された「基本方針案」の見直しを求める署名は短期間に1万4000筆をこえました。
私は委員会の質問で「この『市民意見』がどう反映された『方針』になったのか」質しました。
当局は「反対意見が多いと感じている」としたものの、民間移管方針を変えることは「ありえない」と答えました。
以前の委員会で「基本方針案全体が市民意見募集の対象」ということは確認しています。
「ありえない」ことが「ありえない」。
何のために市民から意見を聞いているのか、怒り心頭です。
○一方で、みなさんの運動で、方針案から「何も変えることなし」という市民世論ではないと当局を思わせた反映がありました。
3つの点での変更です。
①障害をもつお子さんに対応した職員加配の公・民統一化
②地域子育て支援拠点としての機能強化
③重度の障害があるなど特に配慮を要する子どもが在籍する場合のより丁寧な引継ぎ
何れも、具体的内容については鮮明ではありませんでしたが、地域子育て支援拠点については「地域子育て支援拠点事業を担ってきた公営を6カ所移管してどのように『機能強化』するのか」との質問に、「地域子育て支援事業の後退はあり得ない」と述べました。引継ぎについては「より丁寧な」とは何を指すのかという点については「重度の障害がある児童の担当は継続できるようにする」との主旨の答弁でした。
○「6カ所の民間移管方針そのものを変えることはありえない」という当局の答弁をどう見るのか。これは、つまり、市政運営上の根本姿勢ということなのでしょう。
今でも1割しかない公営保育所を更に減らし、そこが担ってきた役割、機能を後退させ、必要な福祉を削減する。民間保育所も苦慮している保育士確保という点での京都市の貢献も大幅に後退させる。これは、市政のかじ取りとして間違っています。
京都市行政の在り方「民間にできることは民間に」と言い「民間にできないことまで民間に」民間移管ありきでひた走る。それが、市民福祉に後退をもたらすことは明らかです。
来年のいっせい地方選挙と再来年の市長選挙を見すえて、市政の在り方を根本から問う運動を広げることが変化を生むと確信しています。
category:市議会
2014年10月25日
来年度からの保育はどうなる?教育福祉委員会審議
月曜日に開かれた教育福祉委員会で以下、3点についても質しました。
①保育の必要度認定に関わって「育児休業中の保育で年長児以外はいったん退所」という国の考え方があるが、従来通り京都市の考え方とすべき。実態が保護者にとって後退してはならない。
②支給認定業務を民間株式会社が行うとのこと。要件にある「児童虐待」「育休中の保育の必要性」「その他市町村が認める事由に該当」などはどのように支給認定されるのか。
③保護者が認可保育所への入所を希望された場合、24条1項で認可保育所は市町村実施義務があり、それに応える義務がある運用上の考え方の説明を。
①については、「新しい規則の方でも市の方が必要と認める場合ということで、育休を取得されたときに上のお子さんが保育が受けられなくなるということを避けるために、市がどのように判定するかという余地を残しており、京都市は柔軟に運用してきたが、ここを変えるつもりはない」と市当局は答弁。
これまで通りの運用とすることを表明しました。
②については、「審査の中身は福祉事務所で判定していくので、入力をしたりする事務作業の委託。実質上株式会社がなにか判断するということにはなっていない」と答弁。
これも、これまでのとおり、福祉事務所での判定という公的観点からの判定の余地に言及しました。
③については、「旧の児童福祉法では原則認可保育所と、無理な場合は小規模等となっていたが、改正後は1項と2項は並列で保育所は原則とはなっていない。保護者のニーズを受け止めながら調整していく」とのべ、「認可保育所にこだわられるのであれば、希望もされていないところへ行きなさいとは申し上げない。希望順位に従って、ご紹介していく」と保護者の希望という話にすり替える答弁を行いました。
改めて、市町村の保育実施義務を果たすことを求めることが、保護者の権利であるという点を広げていくことが必要だと感じました。
①保育の必要度認定に関わって「育児休業中の保育で年長児以外はいったん退所」という国の考え方があるが、従来通り京都市の考え方とすべき。実態が保護者にとって後退してはならない。
②支給認定業務を民間株式会社が行うとのこと。要件にある「児童虐待」「育休中の保育の必要性」「その他市町村が認める事由に該当」などはどのように支給認定されるのか。
③保護者が認可保育所への入所を希望された場合、24条1項で認可保育所は市町村実施義務があり、それに応える義務がある運用上の考え方の説明を。
①については、「新しい規則の方でも市の方が必要と認める場合ということで、育休を取得されたときに上のお子さんが保育が受けられなくなるということを避けるために、市がどのように判定するかという余地を残しており、京都市は柔軟に運用してきたが、ここを変えるつもりはない」と市当局は答弁。
これまで通りの運用とすることを表明しました。
②については、「審査の中身は福祉事務所で判定していくので、入力をしたりする事務作業の委託。実質上株式会社がなにか判断するということにはなっていない」と答弁。
これも、これまでのとおり、福祉事務所での判定という公的観点からの判定の余地に言及しました。
③については、「旧の児童福祉法では原則認可保育所と、無理な場合は小規模等となっていたが、改正後は1項と2項は並列で保育所は原則とはなっていない。保護者のニーズを受け止めながら調整していく」とのべ、「認可保育所にこだわられるのであれば、希望もされていないところへ行きなさいとは申し上げない。希望順位に従って、ご紹介していく」と保護者の希望という話にすり替える答弁を行いました。
改めて、市町村の保育実施義務を果たすことを求めることが、保護者の権利であるという点を広げていくことが必要だと感じました。
category:市議会
2014年10月24日
学童保育をもっとよくしたい! 議第260号をめぐる議論②
教育福祉委員会で行った「放課後児童健全育成事業(学童保育)」についての議論を紹介します。
1,施設・設備の抜本改善を求めました。児童一人当たりの面積1.65㎡は保育園満2歳以上の最低基準(1.98㎡)を下回っており、あまりに狭いと質しました。
当局は「国は学校の余裕教室を利用するように言っており、学校の教室の面積がこの程度かと考えている。1.98㎡は実現可能性からしても難しい」と答えました。
面積基準について満たしていない施設は32か所という前提で審議会や議会でも議論が行われてきました。私は、国が面積を割る児童数を「登録児童」よりも少なくなる「平均利用児童数」を用いるとしていることから、「平均利用児童数」を物差しにした場合に面積基準を満たしていない施設数を資料で請求しました。それぞれ、以下の通りです。※ただし、対象学年の拡大は見込んだものではありません。
<児童一人あたり1.65㎡を満たしていない施設数>
→10施設(児童館分室4・児童館5・学童保育所1)
<児童一人あたり1.98㎡を満たしていない施設数>
→25施設(児童館分室5・児童館15・ほっと広場1・学童保育所4)
私は面積要件をクリアしていく整備について京都市の責任でやるように求め、当局は「条例の基準は児童館だけではなく、ほかの地域学童クラブ、ほっと広場などすべてに適用されるもの。基準に適用するように整備するのは本市の責任である」と答弁しました。
加えて、静養室や台所を整備し、ばらつきのある施設・設備の向上も求めました。これについては「大規模化しているところとか、差が開いていることは認識している」との認識が示されました。
2,職員の配置については児童支援員を1人でなく、2人とすることと処遇の向上を求めました。
職員配置をめぐっては「支援単位が40人になるので大規模なところは40ごとに区切って行って2人のうち一人は有資格者という形になるのでむしろ前進している」と答弁。
あまりに低い職員処遇の向上を求めたことについては「ご要望は従前から受けている。私どもとしても認識している。新制度が始まるにあたって、4年生以上も受け入れるにあたって、処遇上困難なことも出てくる。予算の編成段階で検討していきたい」と答えました。
みなさんから実態をお寄せいただく中で、学童保育の具体的向上の内容が議会論戦の中でも明らかになってきました。職員処遇や施設設備について向上させることの必要性は当局も認めざるをえない状況になっています。引き続き取り組んでいきたいと思います。
1,施設・設備の抜本改善を求めました。児童一人当たりの面積1.65㎡は保育園満2歳以上の最低基準(1.98㎡)を下回っており、あまりに狭いと質しました。
当局は「国は学校の余裕教室を利用するように言っており、学校の教室の面積がこの程度かと考えている。1.98㎡は実現可能性からしても難しい」と答えました。
面積基準について満たしていない施設は32か所という前提で審議会や議会でも議論が行われてきました。私は、国が面積を割る児童数を「登録児童」よりも少なくなる「平均利用児童数」を用いるとしていることから、「平均利用児童数」を物差しにした場合に面積基準を満たしていない施設数を資料で請求しました。それぞれ、以下の通りです。※ただし、対象学年の拡大は見込んだものではありません。
<児童一人あたり1.65㎡を満たしていない施設数>
→10施設(児童館分室4・児童館5・学童保育所1)
<児童一人あたり1.98㎡を満たしていない施設数>
→25施設(児童館分室5・児童館15・ほっと広場1・学童保育所4)
私は面積要件をクリアしていく整備について京都市の責任でやるように求め、当局は「条例の基準は児童館だけではなく、ほかの地域学童クラブ、ほっと広場などすべてに適用されるもの。基準に適用するように整備するのは本市の責任である」と答弁しました。
加えて、静養室や台所を整備し、ばらつきのある施設・設備の向上も求めました。これについては「大規模化しているところとか、差が開いていることは認識している」との認識が示されました。
2,職員の配置については児童支援員を1人でなく、2人とすることと処遇の向上を求めました。
職員配置をめぐっては「支援単位が40人になるので大規模なところは40ごとに区切って行って2人のうち一人は有資格者という形になるのでむしろ前進している」と答弁。
あまりに低い職員処遇の向上を求めたことについては「ご要望は従前から受けている。私どもとしても認識している。新制度が始まるにあたって、4年生以上も受け入れるにあたって、処遇上困難なことも出てくる。予算の編成段階で検討していきたい」と答えました。
みなさんから実態をお寄せいただく中で、学童保育の具体的向上の内容が議会論戦の中でも明らかになってきました。職員処遇や施設設備について向上させることの必要性は当局も認めざるをえない状況になっています。引き続き取り組んでいきたいと思います。
category:市議会