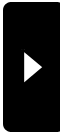2014年10月24日
議第260号などをめぐる議論①
先だっての教育福祉委員会で行った子どもたちの保育などをめぐる議論を紹介します。
1,幼保連携型認定こども園の職員配置や保育時間について、私は保育時間も職員配置もばらばらな状況でどう集団としての保育をすすめるのかと質しました。
当局は「2号(保育必要時3~5才)・1号(幼稚園対象3~5才)・保育と教育を提供するところは、一体的に提供していく。教育の方は早く帰られるが、その後の保育の部分は保育の基準で運用される」。「幼児に対して8時間の教育を行うと言うことはそもそも8時間は年齢的に無理。(教育標準時間は)4時間以上に法令上はおおむね4時間となっており、多少のばすことは禁じられている訳ではないが、おおむね4時間が適当ではないか」と答弁しました。
保育とは何か、教育とは何かの大前提の論議の不足を感じました。就学前のこともたちの保育の中には教育も含まれています。幼稚園の中での学びが8時間びっちりのお勉強とは異なるというのは言うまでもありません。1日という一定の生活時間の中で、発達保障をトータルに取り組むことが大事だと思います。
2,小規模保育・家庭的保育は国家資格保育士の配置での実施を求めました。
当局は「もちろん全部の事業所に保育士という考え方も出てくるが、量の確保ができるのか懸念される」「国の方で最低基準と言われているので、この基準さえ満たせばよいとは思っていない。更に高めていくという気持ちで我々も指導していく」「保護者への情報開示で事業者を選んでいただく。国基準以上の給付単価には入っていないので財源は京都市としての支援も必要となってくることも勘案して今回のことを決めた」と答弁。専門性の担保のある保育の必要性とそれを高める指導がいることは認めました。
3,幼保連携型認定こども園・家庭的保育・小規模保育の設備について、1階を原則とし、2階までとすることを求めました。
当局は「当然私どもも保育室は1階が原則と考える。2,3階ではハードルを高くしている」としつつ、避難階段等の設備の安全性については「国の方で何度も専門家が議論して出てきたもの。それより高い基準を設けるかという判断はなかなか難しかった」と答弁しました。
市としてこの設備があれば子どもたちの安全は守れると決めるというのが今回の条例であり、国が大丈夫としているからということではなく、市としての判断が必要ではないでしょうか。実態をつかみ議論し、安全性を担保していく必要があります。
4,幼保連携型認定こども園・小規模保育・家庭的保育の給食について自園調理を求めました。
当局は「事前の相談の中できちんと自園調理を推奨していくが、100%基準としてしまうと移行が困難になっていくことも考えられるので、国基準通りとしている。決して搬入を推奨しているわけではない。基本は自園調理が基本と考えている」と答えました。前項の安全設備についてもそうですが、広く市場開放を行うことが新制度の目的であり、新規参入の様々な動きが想定されるからこそ、子どもたちの安全と発達を保障するルールが必要だと思います。
1,幼保連携型認定こども園の職員配置や保育時間について、私は保育時間も職員配置もばらばらな状況でどう集団としての保育をすすめるのかと質しました。
当局は「2号(保育必要時3~5才)・1号(幼稚園対象3~5才)・保育と教育を提供するところは、一体的に提供していく。教育の方は早く帰られるが、その後の保育の部分は保育の基準で運用される」。「幼児に対して8時間の教育を行うと言うことはそもそも8時間は年齢的に無理。(教育標準時間は)4時間以上に法令上はおおむね4時間となっており、多少のばすことは禁じられている訳ではないが、おおむね4時間が適当ではないか」と答弁しました。
保育とは何か、教育とは何かの大前提の論議の不足を感じました。就学前のこともたちの保育の中には教育も含まれています。幼稚園の中での学びが8時間びっちりのお勉強とは異なるというのは言うまでもありません。1日という一定の生活時間の中で、発達保障をトータルに取り組むことが大事だと思います。
2,小規模保育・家庭的保育は国家資格保育士の配置での実施を求めました。
当局は「もちろん全部の事業所に保育士という考え方も出てくるが、量の確保ができるのか懸念される」「国の方で最低基準と言われているので、この基準さえ満たせばよいとは思っていない。更に高めていくという気持ちで我々も指導していく」「保護者への情報開示で事業者を選んでいただく。国基準以上の給付単価には入っていないので財源は京都市としての支援も必要となってくることも勘案して今回のことを決めた」と答弁。専門性の担保のある保育の必要性とそれを高める指導がいることは認めました。
3,幼保連携型認定こども園・家庭的保育・小規模保育の設備について、1階を原則とし、2階までとすることを求めました。
当局は「当然私どもも保育室は1階が原則と考える。2,3階ではハードルを高くしている」としつつ、避難階段等の設備の安全性については「国の方で何度も専門家が議論して出てきたもの。それより高い基準を設けるかという判断はなかなか難しかった」と答弁しました。
市としてこの設備があれば子どもたちの安全は守れると決めるというのが今回の条例であり、国が大丈夫としているからということではなく、市としての判断が必要ではないでしょうか。実態をつかみ議論し、安全性を担保していく必要があります。
4,幼保連携型認定こども園・小規模保育・家庭的保育の給食について自園調理を求めました。
当局は「事前の相談の中できちんと自園調理を推奨していくが、100%基準としてしまうと移行が困難になっていくことも考えられるので、国基準通りとしている。決して搬入を推奨しているわけではない。基本は自園調理が基本と考えている」と答えました。前項の安全設備についてもそうですが、広く市場開放を行うことが新制度の目的であり、新規参入の様々な動きが想定されるからこそ、子どもたちの安全と発達を保障するルールが必要だと思います。
category:市議会
2014年10月23日
議第260号、党議員団更なる修正案
議第260号(京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正に)対する党議員団修正案について、10月15日〆切で日本共産党議員団の修正案に対する意見募集をさせていただきました。
市民のみなさんから切実・多岐にわたるご意見をおよせいただき、ありがとうございました。
みなさんのご意見を受けておこなった更なる修正点は以下の通りです。
○学童保育(放課後児童健全育成事業)さらなる改善へ
「保育園児の最低基準が1.98平方メートルなのに、体の大きい小学生がそれ以下の面積基準は理解しがたい」「小学校でも雨の日は喧嘩や衝突が起こりやすいと言われています。ある程度部屋遊びで体を動かし発散させる面積が必要」「放課後ほっと広場などで水道も湯沸しも洗濯機もないところもあり、職員体制も嘱託とアルバイトでよく事故が起こらないものだ」等々、学童保育が児童に健全な遊び及び生活の場を与え、その健康を増進し情操を豊かにする施設として役割を果たすためには、抜本的な向上が必要であることが浮き彫りになりました。
党議員団は一児童あたり1.65㎡という基準を1.98㎡に引き上げの当初提案に加えて、静養室や台所を備えることを規定しました。また、職員の処遇向上に努めることを盛りこみました。
○小規模保育―昼間里親さんの保育士配置がより進む方向へ
小規模保育B型については、市長原案で保育士は2分の1と提案されたことに対し、すべて保育士の配置とすることを党議員団は提案させていただきました。これまでから京都市の保育を支えてこられた昼間里親さんが保育士100%を可能とすることと、小規模保育A型とB型の違いを設けるために小規模保育B型の保育士配置に5年間の経過措置を設けることを加えました。
9月市会最終日に向け、党議員団修正案の成立に向けて全力をあげています。
市民のみなさんから切実・多岐にわたるご意見をおよせいただき、ありがとうございました。
みなさんのご意見を受けておこなった更なる修正点は以下の通りです。
○学童保育(放課後児童健全育成事業)さらなる改善へ
「保育園児の最低基準が1.98平方メートルなのに、体の大きい小学生がそれ以下の面積基準は理解しがたい」「小学校でも雨の日は喧嘩や衝突が起こりやすいと言われています。ある程度部屋遊びで体を動かし発散させる面積が必要」「放課後ほっと広場などで水道も湯沸しも洗濯機もないところもあり、職員体制も嘱託とアルバイトでよく事故が起こらないものだ」等々、学童保育が児童に健全な遊び及び生活の場を与え、その健康を増進し情操を豊かにする施設として役割を果たすためには、抜本的な向上が必要であることが浮き彫りになりました。
党議員団は一児童あたり1.65㎡という基準を1.98㎡に引き上げの当初提案に加えて、静養室や台所を備えることを規定しました。また、職員の処遇向上に努めることを盛りこみました。
○小規模保育―昼間里親さんの保育士配置がより進む方向へ
小規模保育B型については、市長原案で保育士は2分の1と提案されたことに対し、すべて保育士の配置とすることを党議員団は提案させていただきました。これまでから京都市の保育を支えてこられた昼間里親さんが保育士100%を可能とすることと、小規模保育A型とB型の違いを設けるために小規模保育B型の保育士配置に5年間の経過措置を設けることを加えました。
9月市会最終日に向け、党議員団修正案の成立に向けて全力をあげています。
category:市議会
2014年10月16日
障害児保育の水準は後退させてはならない
今日は決算特別委員会の市長総括質疑が行われました。
そこで、自民党会派の議員が保育の障害児加配について取り上げ、市営と民間の格差をなくすことを求めました。市長は「市の保育の在り方を見直す中で民間と市の差をなくす」旨答弁しました。
これまでから民間保育園の関係者は市立に比べて低い障害児加配の改善を求めてこられました。
市営保育所の場合は5段階の加配で、①1対1、②1.25対1、③1.67対1、④2.5対1、⑤5対1。
民間保育所の場合は3段階で、①1対1、②3対1、③5対1となっています。つまり、現行体制では②~④の加配でより公営のほうが手厚い体制が取れるようになっているのです。
いうまでもなく、保護者や保育関係者の積年の改善の願いは、市営を低い水準に下げることでの格差解消ではありません。障害を持つ子どもさんを受け入れる十分な体制確保、低い民間の引き上げです。障害を持つお子さんの保育を保障することは公的保育の揺るがすことができない役割です。党議員団は市営の基準の引き下げはあってはならない、障害児保育の水準は後退させてはならないとそのあとの質疑で指摘しました。
そこで、自民党会派の議員が保育の障害児加配について取り上げ、市営と民間の格差をなくすことを求めました。市長は「市の保育の在り方を見直す中で民間と市の差をなくす」旨答弁しました。
これまでから民間保育園の関係者は市立に比べて低い障害児加配の改善を求めてこられました。
市営保育所の場合は5段階の加配で、①1対1、②1.25対1、③1.67対1、④2.5対1、⑤5対1。
民間保育所の場合は3段階で、①1対1、②3対1、③5対1となっています。つまり、現行体制では②~④の加配でより公営のほうが手厚い体制が取れるようになっているのです。
いうまでもなく、保護者や保育関係者の積年の改善の願いは、市営を低い水準に下げることでの格差解消ではありません。障害を持つ子どもさんを受け入れる十分な体制確保、低い民間の引き上げです。障害を持つお子さんの保育を保障することは公的保育の揺るがすことができない役割です。党議員団は市営の基準の引き下げはあってはならない、障害児保育の水準は後退させてはならないとそのあとの質疑で指摘しました。
category:市議会
2014年10月08日
公立高校選抜「地元の学校に行きたい」が保護者と生徒の願い
昨年大混乱が起きた新しい入試制度後、今年6月に行政が実施した「入学者選抜にかかるアンケート」の京都市・乙訓通学圏の結果の複数回答分が市教委から資料として提出されましたので、グラフにしました。
京都市・乙訓通学圏で公立高校に合格された生徒6220人と保護者4257人からとられたもので、実際は二つのグループに分けてそれぞれの中から3つを選ぶという方式で実施されています。
教育委員会が教育福祉委員会に結果を報告した時には全体が示されていませんでしたので分かりづらかったのですが、こうして全体を示すと特徴がよく見えてきます。
特徴は「通学距離・時間」を選択された方が多いという点です。
校風とあわせて多い傾向が見られますが、保護者は7割以上が選択の中の一つにしています。地元の近い高校に行くという動機が働いているのは明らかです。
教育委員会の決算審議ではそのことを示し、これまでの総合選抜制がそのことにこたえられると指摘しました。「選べる」制度としての単独選抜の意義が強調されてきましたが、本当に「選べたのか」不合格の方や中学校進路指導の先生からのアンケートをやらずしてその検証はできません。
実際に、前期選抜で7000人の子どもたちが不合格になり、1278人が中期選抜で不合格になったことを見れば「選べていない」ということは明らかです。
「中学校進路指導の方や校長会などからも声は聞いている」というのが市教委の答弁でしたので、そのまとめを資料として提出するよう求めました。必要で充分な調査を行って検証する必要があります。

京都市・乙訓通学圏で公立高校に合格された生徒6220人と保護者4257人からとられたもので、実際は二つのグループに分けてそれぞれの中から3つを選ぶという方式で実施されています。
教育委員会が教育福祉委員会に結果を報告した時には全体が示されていませんでしたので分かりづらかったのですが、こうして全体を示すと特徴がよく見えてきます。
特徴は「通学距離・時間」を選択された方が多いという点です。
校風とあわせて多い傾向が見られますが、保護者は7割以上が選択の中の一つにしています。地元の近い高校に行くという動機が働いているのは明らかです。
教育委員会の決算審議ではそのことを示し、これまでの総合選抜制がそのことにこたえられると指摘しました。「選べる」制度としての単独選抜の意義が強調されてきましたが、本当に「選べたのか」不合格の方や中学校進路指導の先生からのアンケートをやらずしてその検証はできません。
実際に、前期選抜で7000人の子どもたちが不合格になり、1278人が中期選抜で不合格になったことを見れば「選べていない」ということは明らかです。
「中学校進路指導の方や校長会などからも声は聞いている」というのが市教委の答弁でしたので、そのまとめを資料として提出するよう求めました。必要で充分な調査を行って検証する必要があります。
category:市議会
2014年10月06日
国保料と学校運営費2つのグラフと公営保育所民間移管続きの論議
10月3日と今日で保健福祉局の2日目審議と教育委員会の決算審議を2つのグラフを使って行いました。
―上段は10年スパンの「国保料」
副市長が「負担は限界に達しつつある」と表明してもなお「国保料の引き下げ」に背を向けてきた京都市。「収支均衡」が目標とまだ安定していないなどと主張していますが、単年度会計も、累積も国保会計が黒字となった今、当局が引き下げを拒んできた理由がなくなりました。
―下段は同じく10年スパンの小学校1学校あたりの運営費
2004年に学校運営費の二割カットと合算執行とする制度変更をしましたが、その水準と比べたら減少したままの状況からもどっていません。
教育行政が子どもたち、先生の声を聞きふさわしい教育予算を確保していくことを求めました。新たな入試制度についても追及しています。ぜひ動画をご覧ください→http://www.ustream.tv/recorded/53639410
加えて、保健福祉局の審議では先日の公営保育所の基本方針案改訂版についてのパブリックコメントでの答弁を再度取り上げました。
「『パブコメは民間移管をするかどうかという基本的な基本方針についてのご意見をうかがっているのではなくて、方針を立てたそのことをどのようにすすめていくべきなのかということを中心に保護者会等でも説明してきた』という10月2日の答弁は方針をどのようにすすめていくかを聞いているだけということか」と質しました。
当局は「昨日の答弁は混同して少し不適切だった。保護者説明会ということでまわっており、保護者の方に説明していることについては方針の下に移管するにあたって留意すべきことなど説明会を行っているもの。反対の意見が多いからと趣旨を変えるというものではない」と答弁。「パブコメについては、基本方針全体について問うている」とはしたものの、保護者説明会についてはすすめるにあたっての説明と答弁しました。私は、市民の意見に耳を傾けない姿勢を批判しました。

―上段は10年スパンの「国保料」
副市長が「負担は限界に達しつつある」と表明してもなお「国保料の引き下げ」に背を向けてきた京都市。「収支均衡」が目標とまだ安定していないなどと主張していますが、単年度会計も、累積も国保会計が黒字となった今、当局が引き下げを拒んできた理由がなくなりました。
―下段は同じく10年スパンの小学校1学校あたりの運営費
2004年に学校運営費の二割カットと合算執行とする制度変更をしましたが、その水準と比べたら減少したままの状況からもどっていません。
教育行政が子どもたち、先生の声を聞きふさわしい教育予算を確保していくことを求めました。新たな入試制度についても追及しています。ぜひ動画をご覧ください→http://www.ustream.tv/recorded/53639410
加えて、保健福祉局の審議では先日の公営保育所の基本方針案改訂版についてのパブリックコメントでの答弁を再度取り上げました。
「『パブコメは民間移管をするかどうかという基本的な基本方針についてのご意見をうかがっているのではなくて、方針を立てたそのことをどのようにすすめていくべきなのかということを中心に保護者会等でも説明してきた』という10月2日の答弁は方針をどのようにすすめていくかを聞いているだけということか」と質しました。
当局は「昨日の答弁は混同して少し不適切だった。保護者説明会ということでまわっており、保護者の方に説明していることについては方針の下に移管するにあたって留意すべきことなど説明会を行っているもの。反対の意見が多いからと趣旨を変えるというものではない」と答弁。「パブコメについては、基本方針全体について問うている」とはしたものの、保護者説明会についてはすすめるにあたっての説明と答弁しました。私は、市民の意見に耳を傾けない姿勢を批判しました。
category:市議会